
2025年9月16日号 (通算25-11号)
HAL農業賞受賞者の取り組みから学ぶ
緑化・デザインの考え方ミニセミナーを開催
東京都狛江市の株式会社和泉園の代表取締役社長で、東京農業大学非常勤講師でもある白井真一さんをお招きして、昨年初めて、緑化・デザインの考え方を学ぶミニセミナーを開催。大変好評だったので、今年も引き続き白井社長をお招きし、2025年8月1日(金)に第2回目のミニセミナーをHAL財団セミナールームで開催した。
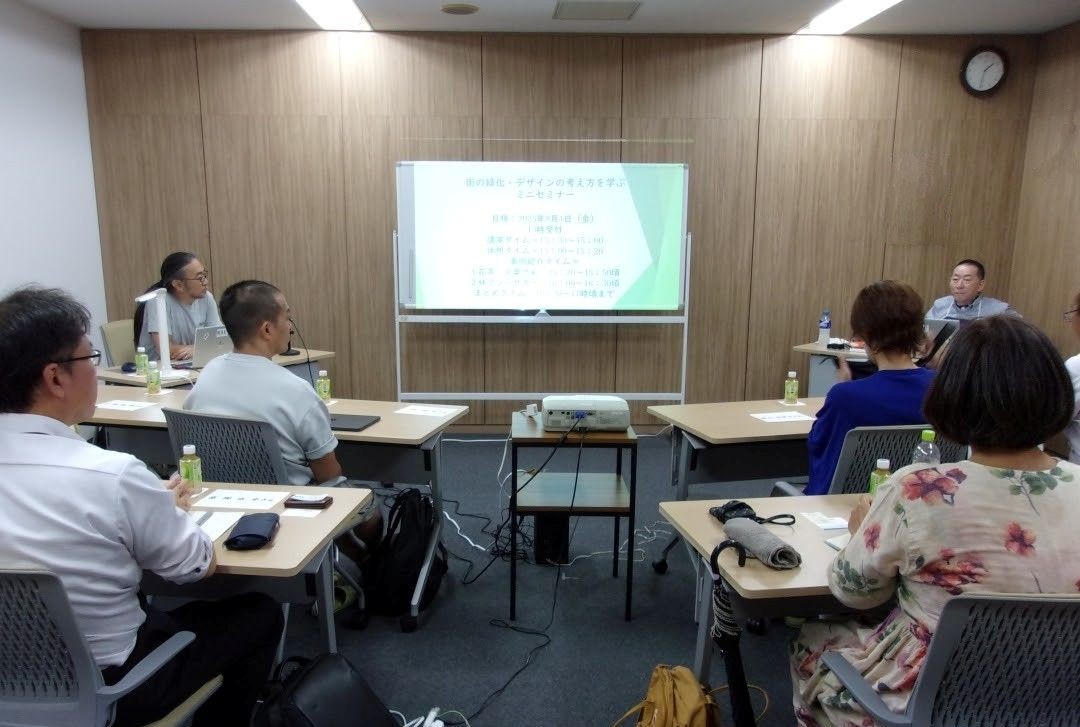
前半は、都市の緑化について、お話を伺った。普段、屋上緑化や公園緑化という言葉をよく聞くが、「緑化」とは、草や木を植えて緑を増やすことであり、緑化によって、美しい環境や、癒しの空間などが整備されてきた。
しかし、現在のように成熟した都市においては、防災や気候変動に対する対策などができていなければ、環境が整うとはいえなくなっている。そこで「グリーンインフラ」という考え方が広まっているという。「グリーンインフラ」とは、「社会のさまざまな課題に自然環境のもつ機能を活用することで、社会資本の整備や魅力のある国土や都市、地域づくりを進める」という考え方。
グリーンインフラの「グリーン」は、緑・植物という意味にとどまらず、緑・水・土・生物などの自然環境が持つ多様な機能や仕組みを指す。それらを積極的に生かすことで、防災・減災や地域復興を主として私たちの暮らしはより豊かに、そしてSDGsのゴールである自然と共生した持続可能な社会へと近づけようというのだ。
グリーンインフラを推進することで、地球温暖化の緩和や浸水対策、生き物の生息・生育空間の提供など環境への様々な効果が期待できる。また、グリーンインフラを適切に運用していくことで、健康の促進や環境教育などの人間活動に効果がもたらされるということなどを学ぶことができた。
後半は、緑のビジネスの話。造園装飾を多く手掛ける和泉園ならではの、ドラマやCMセットの裏話を聞くことができた。なにげなく見ているドラマやCMの植物や庭は、苦労の上に作られていることがわかった。
また映像のみならず、ファッションショーの装飾や、今年は万博でのイベント用の梅の木の制作など、仕事は多岐にわたっている。今後のさらなる広がりが気になるところだ。
つづいて、今年は、第13回HAL農業賞 優秀賞を受賞した、有限会社花茶の小栗美恵さんと、HAL農業賞アンバサダーで、「まちづくりコーディネーター」で、「絵師」でもある林匡宏さんを話題提供者にお迎えした。
小栗さんは、花茶農園を営む一方で、農村風景を愛でながら美味しい季節の料理を楽しめる、ふれあいのスポットとしてファーム花茶をオープン。農村の風景を「庭」に・・・まさに、ガーデンの原型だ。さらに、ファームの敷地内に自らガーデンを作るなど、緑化を進めている。
林さんは、渋谷の都市デザインや、札幌市初のPark-PFI事業「百合が原公園再整備プロジェクト」を手掛けている。Park-PFIとは、民間事業者が都市公園の中にカフェやショップなど公園の利便性が向上する収益施設を設置し、その収益の一部を公園の管理や整備などに活用する制度だ。民間事業者の創意工夫により市民サービスの向上や公園の活性化、行政の財政負担の削減を図ることができるとして、全国的にも広まっている。
こうした公共的空間をいかに活用していくか。その一つが、まちなかの緑化だ。まちなかに、緑や畑を作ることで、環境整備はもちろんのこと、人々が「つながる」場所ができるとのこと。また新たな緑化の可能性を知ることができた。
参加者は、札幌市内の生花業や苗・鉢物業の方、畑作農家、まちづくり、公園関係の方など。講演会終了後の懇親会では、ビジネス上の意外なつながりがあることが多々わかり、大いに盛り上がっていた。緑化の話を通じて、ここでもまた「つながり」の大切さを意識させられた。今後もこの「つながり」から新たなコラボなどに発展することを期待したい。
HAL農業賞受賞者を招いてのセミナーなど、ご要望ありましたら、HAL財団までお寄せください。
(記事:総務部 山京)

