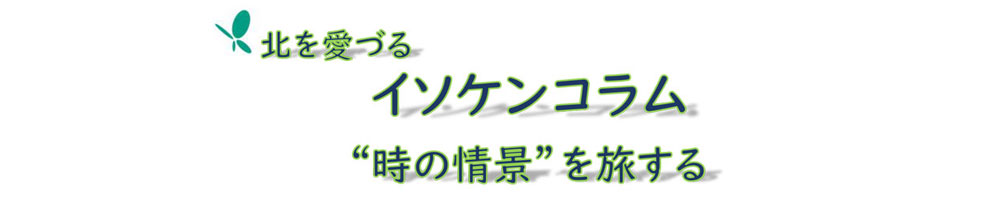2025年8月28日号
通算25-03号
農業で学ぶ~小学校に「農業科」教育を~
14年前の「東日本大震災」の際、科学者が思わずもらした「想定外」という言葉に、「生命誌」研究の道を拓き、人間の「在りよう」を問い続けてきた生命科学者・中村桂子さんは強い違和感を持ったという。自然の力や大きさは想定などできないのに、科学技術の世界にありがちな“人間がすべてを制御する”という思考からの発想だというのだ。科学知識のない私も「上から目線」を感じ、頭を捻ったものだ。
自然の中にいる人間が、自然と向き合わずにきた結果としての「大量生産・大量消費」が引き起こした、エネルギーや地球環境をめぐる歪み…。中村さんはそうした課題に向き合い近代文明を問い直していくためには、「人間は生きものであり、自然の一部」という基本に立ち返るほかないと語る。
2022年8月、その中村さんを、美唄市にある芸術文化交流施設「アルテピアッツァ美唄」にお迎えし、「いのち愛づる生命誌講座」を開催した。その準備の過程で、福島県喜多方市が中村さんの提言を踏まえ、2007年から日本で初めて、小学校教育に「農業科」を組み込んでいたことを知った。同時に美唄市も喜多方市に学び、12年前から「農業体験」学習に取り組み、「副読本」を作成していたことも判明。その繋がりに驚きつつ中村さんをお迎えしたのだが、講演を前に中村さんから貴重な助言をいただくことになる。
「農業体験は今や当たり前。だが、あくまで体験の域にとどまる。小学校の「時間割」に、国語、算数、理科、社会と同じように“農業科”が入っていることが大事。その継続が子どもたちの生きる力を育む…。」中村さんの確信に満ちた言葉が胸にしみた。
その助言から9ヶ月後の2023年春、美唄市は小学校での「農業科」授業をスタートさせた。中村さんによると、喜多方市が「農業科」を開始した時、多くの自治体が来訪し、誰もが感嘆して「わがまちでも…」と語ったという。だがその後、喜多方市に続く自治体は一つとしてなく、15年の歳月が流れた。
美唄市は中村さんのアドバイスを踏まえて、それまでの「農業体験」を「農業科」に、「農業体験副読本」を「農業科読本」へと進化させ、全国2例目の先駆的自治体となった。
中村さんは、“農業で学ぶ”ことの意義を次のように語る。「農業科は、自分で食べ物を作り自立の力をつけると同時に、全ての生きものが仲間であり、みんなで支え合いながら生きていく大切さを学ぶ楽しい時間…。」
中村さんは、喜多方市が農業科をスタートさせる前から“小学校で農業を必須に”と提唱してきたが、地球環境の今を思う時、「農業科」は、地球に生きる上での謙虚さや、同じ生きものに向けた優しい眼差しを身につける大切な社会装置といえる。その意義を胸に、HAL財団内に過日、「小学校“農業科”教育イニシアティブ」を立ち上げた。“農業科”の輪を広げていく“旗”を掲げた日本初の「チーム」。中村桂子さんも共同代表として参加してくださる。遥かな道のりだが、「次なる“百年の計”」に連なる道と信じて前を向いていきたい。
※朝日新聞より加筆修正