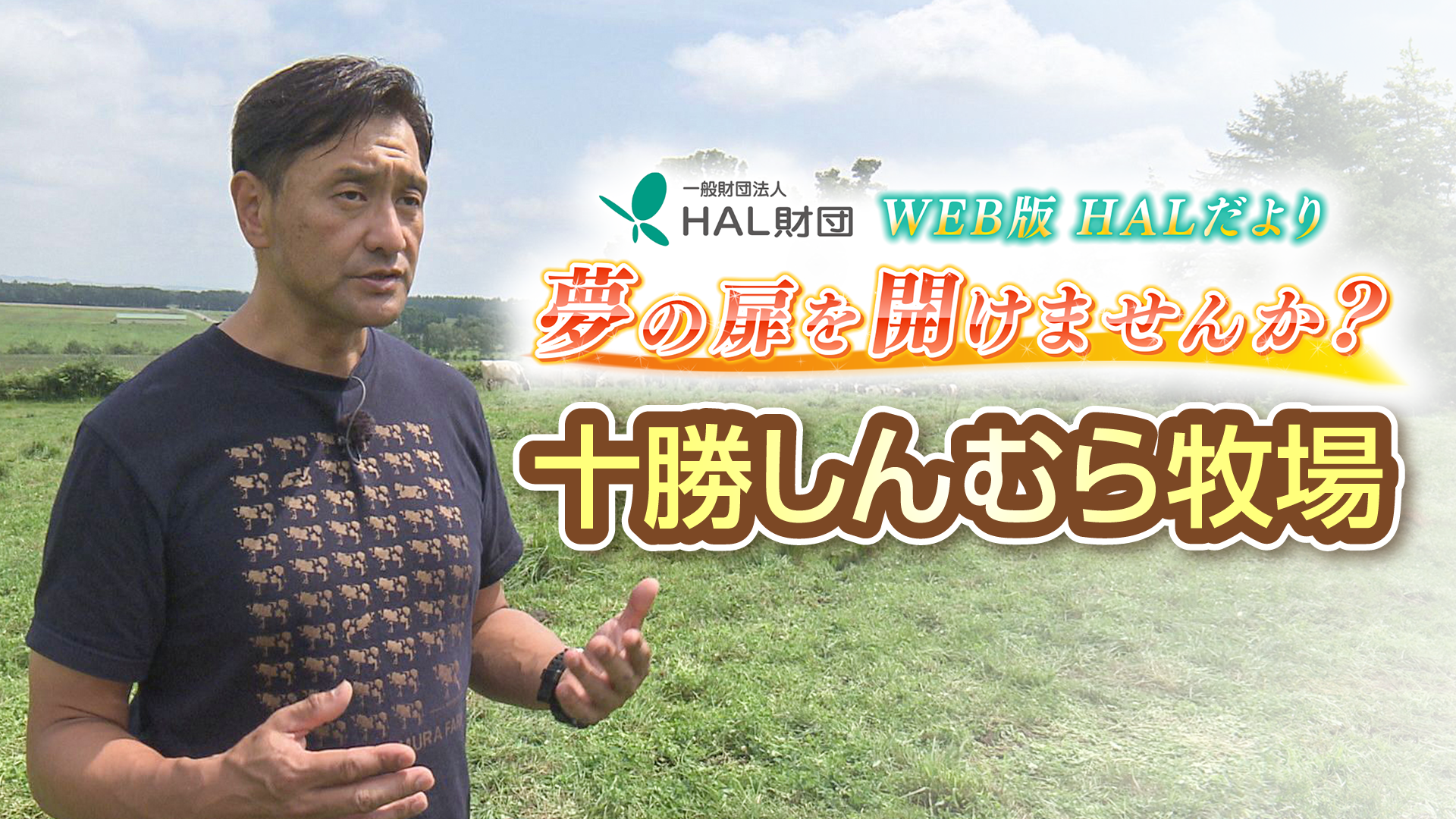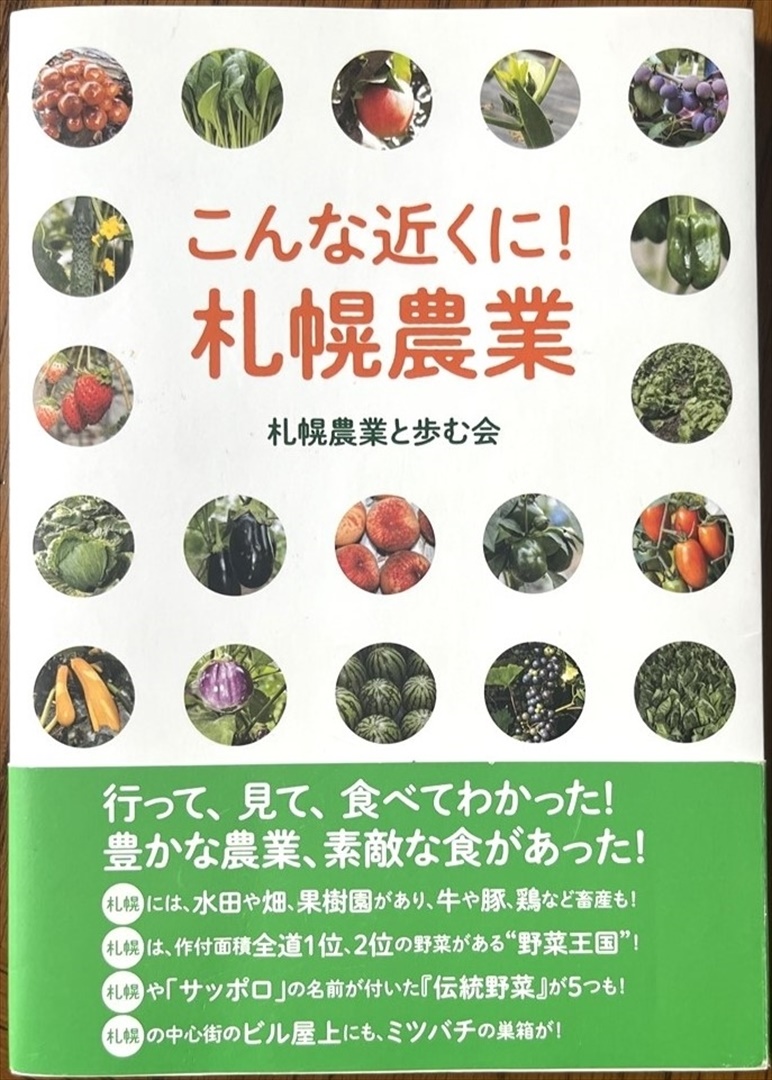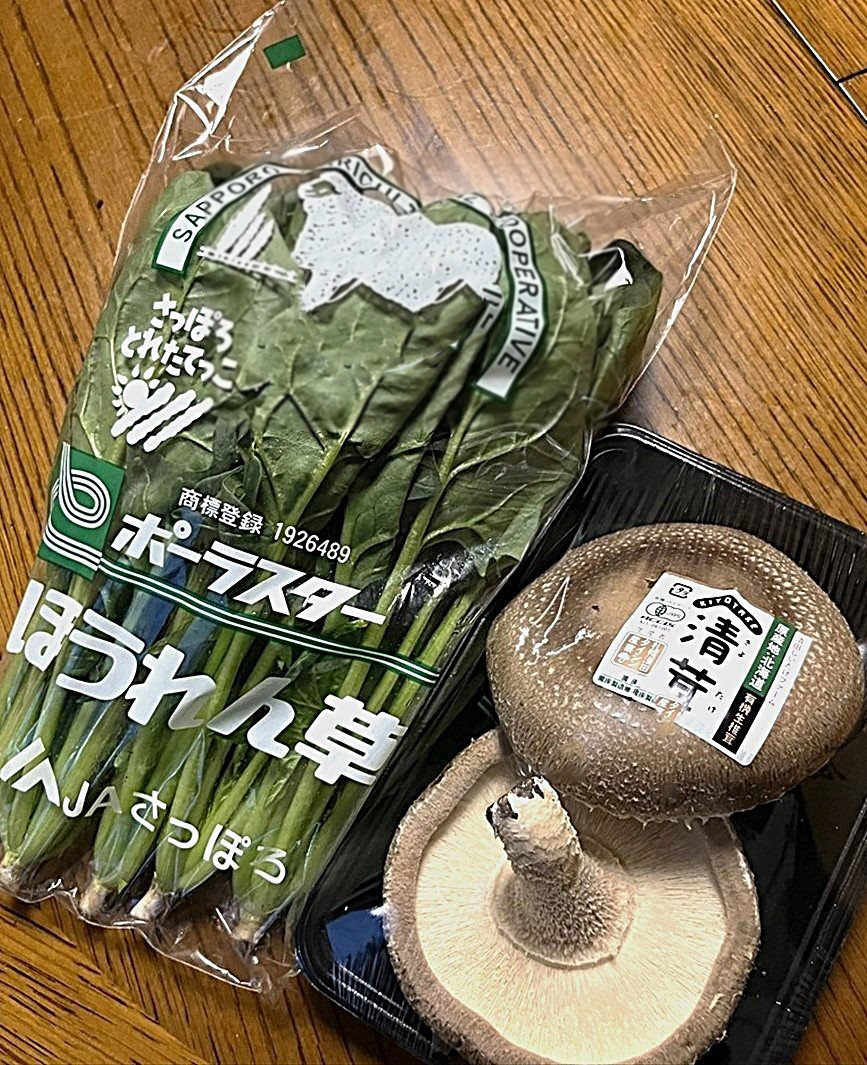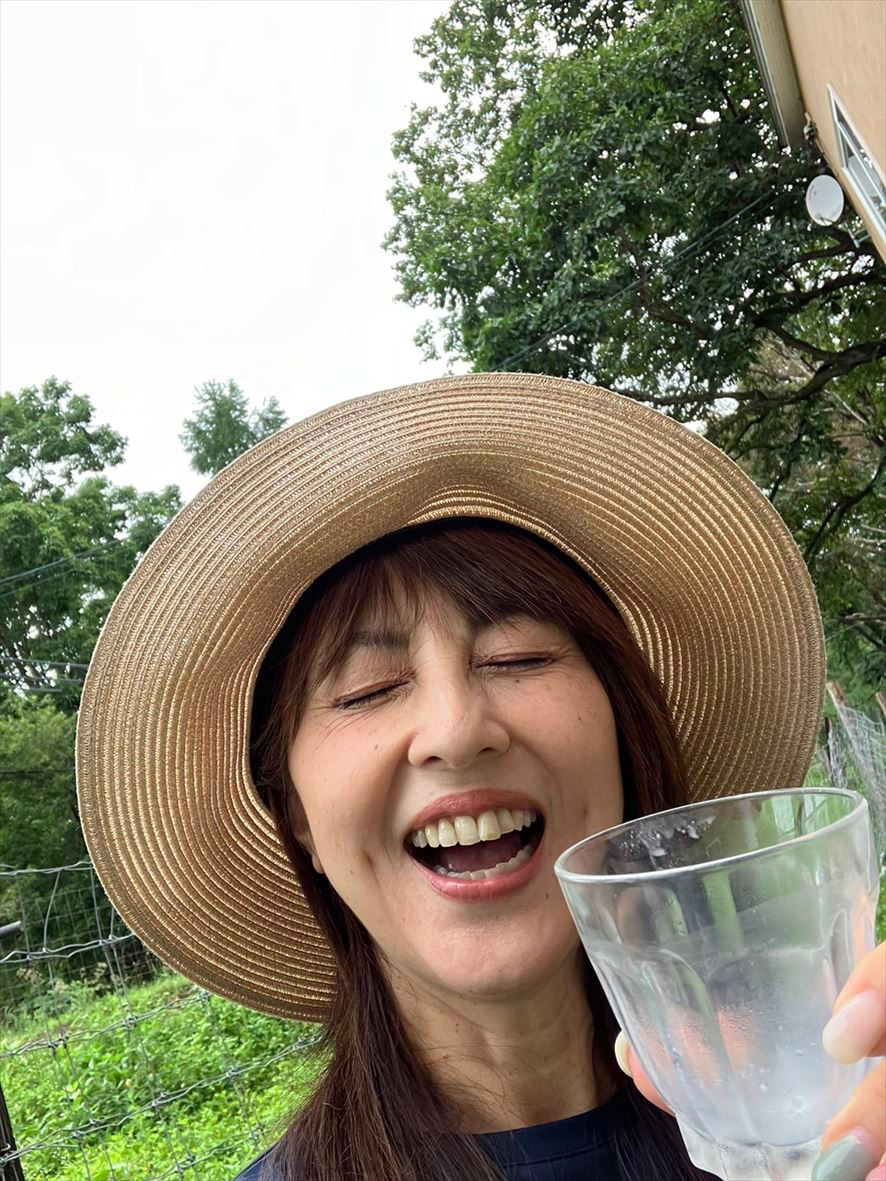2024年11月19日号(通算24-34号)
白い花咲くそば畑から
**今回の「WEB版HALだより」は、昨年大変好評だった、農業とは縁のなかった写真家・藤田一咲(いっさく)さんに、北海道農業の現場を見てもらい話を聞く企画の第2弾です。今回も3カ所の現場に足を運んでいただき、HAL財団・上野貴之が聞き手となる対談形式でお届けします。私は敬愛の気持ちから、今年も一咲さんと呼ばせていただきます。
(HAL財団 企画広報室 上野貴之)
そばの生産量日本一は?
●上野:一咲さんには昨年に引き続き、今回も北海道農業の一端を見てもらいます。そこからどんな風景、未来が見えてくるのか楽しみです。さて、今回の最初の取材地は新得(しんとく)町でそばを栽培する「はら農場」。
一咲さんは東京の人だから、そばといえば信州、つまり長野市戸隠(旧戸隠村)のそば、いわゆる「戸隠そば」がすぐに頭に浮かぶでしょう?
★一咲:「七つ長野の善光寺、八つ谷中の奥寺で、竹の柱に茅の屋根、手鍋下げてもわしゃいとやせぬ、信州信濃の新そばよりもわたしゃあなたのそばがいい」。
●上野:「あなた百までわしゃ九十九まで、ともにシラミのたかるまで」って? いや、それは男はつらいよの寅さんの啖呵売(たんかばい=ごく普通の品物を巧みな話術で売りさばく商法)のセリフですけど、信州信濃〜の部分は都々逸(どどいつ=江戸時代に生まれた、七・七・七・五の口語定型詩)です。
★一咲:「そばどころは信州」のイメージは江戸時代には確立されていたんですね。ぼくがそばは信州のものと思っていても不思議ではないですね。
●上野:そばはどこで作られていると思いますか?
★一咲:日本三大そばというくらいですから戸隠そばの長野県、出雲そばの島根県、わんこそばの岩手県あたりになるでしょうか?
今回、北海道のそば畑に取材に行くと聞いて、北海道でもそばを作っているんだと改めて思いました。改めて、というのは、写真界隈では真っ青な空の下で白い花が一面に咲く北海道のそば畑はとても有名ですから。でも、それは観光客誘致のためのものだと思っていました。
●上野:あのですねえ、日本一のそばの生産地は北海道なんです。
★一咲:え、えええ?! それは知りませんでした。北海道の麺といえばラーメンでしょう? 札幌の味噌ラーメン、函館の塩ラーメン、釧路と旭川の醤油ラーメンなどが有名ですよね。北海道のそばで有名なブランドとか、全国的に展開している名の知れた有名店とかあるのでしょうか?
●上野:そうかあ、北海道のそばは日本一の生産量でも、全国的にはあまり知られていないのが現実なのかも知れないなあ。生産量全国第1位の幌加内町の幌加内そばとか、生産量全国第2位の深川市の多度志そば。そして私たちがいま向かっている新得町のそばは、北海道産ソバの代名詞と言われてます。町内を通る国道38号は通称「そばロード」と呼ばれ、北海道のそば畑の写真はここで撮られたものがほとんどでしょう。


そば畑の匂いの秘密
●上野:新得町は東大雪の山々と日高山脈に抱かれた山麓地帯にあります。ここは冷涼な気候で昼・晩の寒暖の差が大きいので風味豊かな美味しいそばが育つのです。
★一咲:寒暖の差が大きいほど植物は強く育つからですね。
●上野:強く育つにはエネルギーを蓄える必要がある。それがそばの旨味、甘味に大きく影響するわけです。
★一咲:北海道の気候は元々そばの栽培に向いているんですね。最近の厳しい暑さは、今後の生産量に影響しそうですが。
●上野:一咲さんはそば畑を見たことがありますか?
★一咲:こんなに近くで、しかも満開の時は初めてです。しかもモンシロチョウやハチがたくさん飛んでいて、なんだか天国のような光景ですね。でも、ちょっと臭いような気もします。
●上野:小さくて可愛らしいそばの花ですが、よく言われるのが肥料のような、動物のフンやお酒が発酵しているような独特な匂いがするでしょう? そばは受粉が難しい植物で、人間には臭いけど虫の好む匂いを発して、虫を呼び寄せているのです。本州のそば畑周辺では、この臭いで近隣の住民からクレームがあることもあるとか。
★一咲:それでここにはモンシロチョウやハチがたくさんいるんですね。でも気にならないくらいの匂いです。もっと匂いが強いくらいの方が虫も集まりそうですね。


美味しいそばは土作りから
●上野:一咲さん、ここの匂いはそばの花だけではないのです。はら農場は有機栽培のそば畑ですが、鶏糞と馬糞を合わせた堆肥も独自に自分で作っているので、その匂いでもあるんです。
★一咲:そこまで手間と時間をかけてそばを栽培しているんですね。
●上野:ここで大切にしているのは土作りからなんです。堆肥の他にクローバーなどの草も使っています。いわゆる緑肥です。クローバーは植えているだけで緑肥効果があり、畑にすき込むと堆肥としても利用できます。
★一咲:昔のレンゲみたいな感じでしょうか。どちらも化学肥料とは違う良さがあって、一緒に使うことでさらなる効果が望めるんでしょうね。でも緑肥はもう一つ作物を育てるようで大変ですね。
●上野:北海道のそば栽培の多くは「キタワセソバ」です。新得町では他に「ぼたんそば」や「レラのカオリ」を栽培していますが、はら農場では主に「キタノマシュウ」というそばを栽培しています。そばと緑肥の種まきの時期のバランスなどが難しいこともいろいろありそうですが、独自のノウハウがあるのでしょう。よく見ると、そばと一緒に他の植物も一緒に育っていますね。
★一咲:自然に近い環境で育てると、気候以外にも競争力が働いて元気で丈夫に育ち、より美味しいそばになりそうです。はら農場のそばを食べるのが楽しみです!


そば栽培は命がけ
●上野:一咲さん、驚かすわけではありませんが、どこからか何か生き物の気配がしませんか?
★一咲:たしかに! これは野良猫の気配ではないですね!
●上野:ここはうっそうとした森に挟まれたほ場(農地を指す言葉)ですから、熊が出てもおかしくない。森の中に入ると、木の幹に鋭い彫刻刀で掘られたような熊の爪とぎ痕があちらこちらに見られますよ。これを人間にされたら、たまったもんじゃない。最近は熊の出没情報が多いし、悲惨な事故もあるので気を付けないと。
★一咲:気楽に天国のように綺麗なそば畑なんて言ってる場合ではないですね。そばの栽培は熊に襲われる恐怖と背中合わせ、命がけのところがありますね。ただでさえ、大変なそばの栽培にそんな危険も加わるとは。
●上野:熊の問題は、ここだけではなく北海道全体に言えるのですが、消費者はそんなことは考えませんね。
★一咲:その分を価格に乗せないといけませんね。先ほどの、受粉の難しさを考えると、これだけ手間をかけて栽培してもどれだけの量が収穫までいけるのかも気になりますし。畑一面咲いてる見た目の花の量から、いつも豊作のように見ていましたが、思ったほどではないのかもしれないし、また想像できない苦労もあるんでしょうし。

夏の猛暑に加え、熊出没の恐怖の中でそばが栽培されていることは今まで想像できませんでした。


新そばの味
●上野:一咲さん、新得町の毎年恒例「しんとく新そば祭り」(9月29日開催)から今年の、はら農場の新そばをお届けしますよ!
★一咲:新そばと言っても、今まではハッキリとその味を実感したことがないので、それはすごく楽しみです! 土作りからこだわって作られたそばですから、ぼくの期待は大いに高まります。
●上野:はら農場のそばは「原氣(げんき)蕎麦」というブランドですが、その味、活動と地域の貢献がともに評価され、一般社団法人日本蕎麦協会の全国そば優良表彰事業で最高賞に次ぐ「農林水産省農産局長賞」を2021年に受賞しているお墨付きの品質です。
★一咲:上野さんから送られてきたのは、原氣蕎麦「新そば なま(八割生そば+飛魚つゆ付)」「新そば 十割 乾麺」「十割 石臼」そして「そばの実」に「蕎麦の妖精」というスパイスミックス。
もちろん、すぐに生そばからいただきました。まず色が濃い。これは濃厚な味わいが期待できる。しかも、茹でなくていい。電子レンジでチンできる。そばの香りの高さ、歯ざわりの良さ、味は甘味と旨みが強くちょっと木の実のような、濃厚なそばの風味。この味は初体験! これまでに食べたことのない美味さ。蕎麦湯も濃厚。これは実際に食べてみないとこの味はわからない、伝えられないのが残念です。
●上野:食べてばかりいないで、北海道農業的にはどう見られましたか?
★一咲:北海道のそばの生産量は全国でも圧倒的な一位。でも(少なくともぼくの周りでは)知名度が低い印象です。
売るための努力はしなくても十分に売れているのでしょうが、ブランド力を高めることも大切だと思います。
そばはたんぱく質、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラルの五大栄養素が米や麦に比べてもいい、また必須アミノ酸もバランスよく含んでいると言いますから、もしかしたら主食になりうるのではないでしょうか。今年は米不足もありましたしね。そばで北海道農業もさらなる展開が望めそうですね。麺としてだけの食べ方以外も提案されると良さそうですね。また少し変わった味の品種を作るとか。
●上野:はら農場さんはそもそも「化学肥料や合成農薬に頼らずに、自然が持つ本来の力を活かして主食になりうるもの」を作りたいと思ってそば栽培を始めたようです。はら農場ではそばの実で造った発泡酒もあります。これからそばを使ったいろいろな商品の展開があるかもしれません。
★一咲:そばは外国でも生産されていて、食べ方もいろいろあるでしょう。伝統の食べ方の他の選択肢が増えると楽しいですね。




七味代わりに。少量で十分なアクセントになります。

藤田一咲(ふじた いっさく)
年齢非公開。ローマ字表記では「ISSAQUE FOUJITA」。
風景写真、人物写真、動物写真、コマーシャルフォトとオールマイティな写真家。
脱力写真家との肩書もあるが、力を抜いて写真を楽しもうという趣旨。
日本国内は当然、ロンドン、パリなどの世界の都市から、ボルネオの熱帯雨林、
アフリカの砂漠まで撮影に赴く行動派写真家。
公式サイト:https://issaque.com
写真:ISSAQUE FOUJITA